サピエンス全史 第1部(1)
ブログをやり始めた当初は「書評でもやろうかな~!」と思ったのに全然やっていないのはどうしたことだろう。
理由は単純、面倒だからなのだが、そうはいっても他人が代わりにやってくれるわけでもないので、やはり自分で書くしかない。
というわけで、今回は最近読み始めた「サピエンス全史」の上巻、第1部の前半に関して、どういったことを言っているかとどう思ったかを綴っていく。
なぜこの本を選んだかと言うと、「今を生きる全ビジネスマン必読の新しい教養書」なる”強い”ワードが書かれていたからである。
人類史における「三大革命」
ハラリはまず、人類文化の発展が紡いできた歴史の中で、3つの大きな革命があったと主張する。人類が他の動物と一線を画し、文化の発展、すなわち歴史が始まるきっかけとなった「認知革命」、その歴史を加速させた「農業革命」、そして「科学革命」である。本著はこれら3つの革命が人類に、そして地上の生き物たちにどのような影響を与えたかについて記述している。
第1部では全4章構成で認知革命について扱っており、この記事では前半の第1章・第2章が何を論じているか、そして私がどう思ったかについて記述する。
人類はどこから来た何者か
学者の説では、人類は250万年前の東アフリカでアウストラロピテクスから進化して生まれた。その後、今から200万年前にアジア・ヨーロッパ・北アフリカへ版図を広げ、それぞれの環境に合わせて進化していった。そして、今から1万年前になるまでは、この地球上にホモ・サピエンスの他に、ホモ・ルドルフェンシス、ホモ・エレクトス、ネアンデルタール人などのいくつかの人類種が暮らしており、1万年前より後ろの時点では何らかの理由により、サピエンスが現代のようにこの地球に生きる唯一の人類種となった。
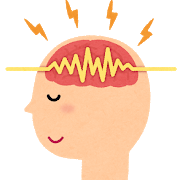
それぞれの人類種には体格などの特徴が見受けられるものの、大きな特徴点がある。それは、巨大な脳を持ち、直立二足歩行をするということだ。この二つの特徴によって、人類は高度な思考力を獲得し、自由になった手で精巧な作業をすることが出来るようになった。その反面、脳はその燃費の悪さから、エネルギーのリソースを体の他部位から奪い取り、結果として筋力が弱くなった。また、巨大な脳を支えながらの二足歩行は肩こり・腰痛という、四つ足の動物では経験することのない苦痛を人類に課した。
この2つの特徴が出産に関して与えた影響はとりわけ大きい。というのも、直立二足歩行によって女性の骨格は以前よりも狭くならざるをえなくなり、同時に発達した巨大な脳が出産の際に大きな障害になる。そこで、人間は子供を成長する前の早期の姿で出産することにより、このジレンマを乗り越えた。しかし、生後すぐに動けるようになる他の哺乳類の動物とは違い、人間は自分で生きて行けるようになるまでに、長い時間をかけて年長者の世話になる必要がある。しかし、この手間のかかる出産と子育てこそが、人間が社会性を育むきっかけとなった。

人類は巨大な脳と精巧な動きが出来る手を持ったことで、道具の作成、高い学習能力、社会構造を手に入れ、40万年前には火をコントロールできるようになったことで更なる飛躍を遂げた。火は光と熱の源となり、武器となる。また、火を使って調理をして食物を消化しやすくなったことで、食事に要する時間を削減すると共に、脳と同じくエネルギーのリソースを食う腸を短くした。腸が短くなり、エネルギーが他のところに回せるようになったことで、人類の脳は更に進化したのではないか、という言説もある。
15万年前の人類は、火の恩恵に浴していながらその勢力は未だ大きくはなかった。これは現生人類に連なるホモ・サピエンスも例外ではなく、この時点ではアフリカ大陸の片隅に細々と暮らす存在に過ぎなかった。学者によれば、およそ7万年前にアラビア半島に広がり、そこから短期間でユーラシア大陸全土を席巻したという。
この時、ホモ・サピエンスが移住する前に定住した他の人類がどうなったかについては、2つの学説が存在する。1つは「交雑説」というもので、ホモ・サピエンスが他の人類種と交配し、現生人類はその結果生まれたものだとする説である。確かに、現生人類の一部には、過去に生きていた他の人類種のDNAを持っている人種が存在するが、その交雑の割合は数パーセントにすぎず、部分的に正しいという程度にとどまる。
それでは、いかにして他の人類種が消えてしまったのかについては、「交代説」が答えを提示する。これは、他の種が何らかの理由でゆっくりと死に絶えてしまった結果か、もしくはホモ・サピエンスが他の人類種を大量に虐殺するなどして、地上に君臨するようになったという。
いかにしてサピエンスは栄えたか――認知革命

なぜ、ホモ・サピエンスだけが地上に生き残ることが出来たのか。その答えは言語・認知的能力に起こった革命的現象にある、とハラリは論じる。言語自体は人類に限らず、単純なパターンではあるが動物も持っている。それでもなおサピエンスの言語が特別な理由について、ハラリは2つの学説を提示している。まず、膨大な表現パターンを持っている点。もう一つが、噂話をすることによって、より強固な協力体制を敷くことが出来る点だ。
しかしながら、ハラリは自説として、ホモ・サピエンスの言語が持つ真の特徴は、「まったく存在しないもの、見たことも触れたこともないものについての情報を伝達する能力」にあると語る。研究によれば、噂話によるコミュニケーションで統制の取れる集団の上限人数は150人と言われている。
しかし歴史は、人類が150人の上限を超えて協力体制を敷けることを示している。太古の都市国家しかり、中世のカトリック修道会しかり、近代の国民国家しかり、現代の企業しかり、人類はその成員がおそらく、「共通の神話・ストーリーという虚構」を伝達し、それを信じることによって、互いの顔も知らない人間同士がこれらの組織を運営したり、取引をしたりすることが出来た。
また、人類が生み出す虚構は柔軟性を持つ。チンパンジーは生物学的に父権主義的な社会を構築し、それが変わることはない。しかし、人間は保守的な家庭で育てられながら、大人になってリベラルになることも出来るし、資本主義社会で育った人間が社会主義のイデオロギーに染まることも出来る。
思うこと
ハラリ氏はどうやら、人類の発展は虚構を生み出し、それが信じられるよう意味付けすることに裏付けされてきた、というのが説の根幹にあるらしい。読む限り、本の中では150人を超えた協力関係の構築をするにあたり、共通の神話を信じることが役に立ったというのは「おそらく」というレベルで留められている。こうした面から、神話が実際に役に立ったかどうかの因果関係は一概には言い切れないものを感じる。
とはいえ、現に我々は巨大な組織が運営されている様を目の当たりにしているので、そこに何らかの引力が働いていると見るのは自然な気がするし、行動の種火となる思想の部分に、修道会で言うところの神、国民国家で言うところの国民主権や人権といった概念が鎮座し、それが人々に影響を与えていると見るのは自然なことかもしれない。

また、今日の我々は、多くの人がそれぞれの主張を振りかざして対立しあう分断の構造を目の当たりにしている(ような気がする)。老人と若者、企業と労働者はハラリ風の言い方をするなら共通の神話を持っていないので到底折り合わない。ツイッター上で社会学者や女性の味方を名乗る人たちは、自分たちの考える正義という虚構をあちこちに押し付けようとして、見当違いな方向に多大なコストを払わせようとしながら叩かれている。
こうした争いは今後も増えるばかりだろうし、今は少し変わった人たち程度で認識されているであろう男女間の社会的再生産に関わるいさかいも、時を経て一般化される可能性だってある。こうなれば人間がその数を勝手に減らし、取り返しのつかないことになるかもしれない。
この虚構同士の小競り合いが数十年前と比べ、随分と多くの派閥がやり合うようになったように見えるのは私だけだろうか。また、小競り合いの頻度が増えているのはどうにも、通信技術の発達によって、人々が触れられ、発信することのできる情報が量・質ともに爆発的に向上したことと無関係とは思えない。
もしそうだとしたら、多彩なイメージの伝達と噂話、虚構の伝達能力によって栄えたという我々ホモ・サピエンスが、それによって滅びることになるとは実に皮肉な話ではないだろうか。